CMTミュージック・ディレクター 中野振一郎さんインタビュー
掲載日:2003年10月21日
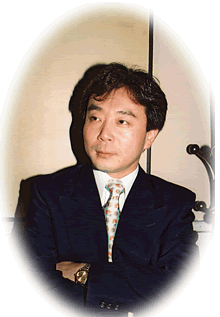
舞台では、独奏者としてメンバーと丁丁発止のやり取りをみせるスタンデイジ氏。普段はどんな音楽家なのだろうか。巨匠の「オフステージ」について、コレギウム・ムジクム・テレマンのミュージック・ディレクターを務めるチェンバロ奏者の中野振一郎さん=写真=に語ってもらった。
――サイモンは京都人?
英国は大人の国。欧州の他の国と違い、奥ゆかしいと言うか、気持ちをあまり外に出さず、「言わんでも分かるやろ」みたいな、阿吽(あうん)の呼吸を尊ぶ風土がある。京都生まれのボクにしたら、「あ、仲間がいやはった」いう感じです。英国に行くと、ホッとするのも、この国民性のお陰。こと音楽の話題になると彼も結構、熱弁をふるうけれど、最後には必ず「ワシもよぅ分からへんけどな」と遠慮深いコメントが付く。ただ、難しい曲やる時には「ぐずぐず練習なんかしてんと!これくらいパッと弾けなアカンの!!」という厳しさもある。こんなとこにも京都に似て、かつて貴族のいた国ならではの気質があると思います。
――サイモンは天才肌!
彼、音楽に集中すると、何でも忘れてしまうんです。10年ほど前、京都に彼の公演を聴きに行ったんですが、その時は靴を宿に置いてきたらしい。靴下のまま、楽屋の辺りをペタペタ歩いてた姿を、古楽界に君臨してる名手のイメージと重ならなくて、妙でした。ボクのロンドンデビューの際、共演する関係でホームステイさせてもらった。この時、近所の民家がチェンバロの練習場所になった。お昼、迎えに来てくれると約束したのに、ナンボ待っても現れないんです。諦めて一人で戻ったんですが、案の定、彼は自室で練習の真っ最中。なぜか「オマエは待ってたに違いない!」と怒鳴られ、参った思い出があります。
――サイモンは学究肌??
ヴィヴァルディの「四季」演奏で脚光を浴びたサイモンですが、実は、知られざるイギリス人作曲家の作品が大好き。アーン、ボイス、グリーン…。ご存知ですか? 皆、ヘンデルの同時代人です。お決まりのパターンを繰り返すような一見、単純な曲調の中に、わざと凝った和音を潜り込ますなど、読み間違うようなトリックが隠されている。さすがアガサ・クリスティーを生んだミステリーの国です。サイモンは、こういった曲をサッと弾くのが堪らなく好きみたい。でも、彼のライフワークはフランスのルクレールの作品。この作曲家には執着を持っていて、ボクと共演する時も毎年、必ず新しい曲を用意してきます。
――サイモンは感性派…
ボクの学生時代、古楽の"本場"とされてたのはオランダとベルギーでした。英国の音楽家は「指が回ってない」「音が汚い」なんて言われることもあった。でも彼と共演してみたら、ともかく音がキレイでした。それに音楽づくりに無理がない。イタリアやフランスの作品で音合わせしたら、曲の構造をしっかり押さえて、主導権を取ってくれたり、こちらを立てて、脇役に回ってくれたり。「出処進退」の妙というか、その切り替えの何と巧みなこと。それから、学究的なアプローチの充実はもちろんですが、譜面から立ち上る、曲の "薫り"を嗅ぎ分けて、臨機応変に弾き分けるカンの鋭さにはホンマに敬服してます。
――サイモンは「帝王様」
彼がソリストの活動を始めたのは、50歳を過ぎてから。以前は弦楽四重奏団やオーケストラのコンサートマスターとしての活躍が主だったので、舞台である種のワガママを通し、自分の"華"を見せ切る「芸」は修羅場を重ね、身に付けたんです。彼の譜面は、手書きでどうも読みにくい。練習で、こちらが少しでもトチルと演奏を止め「なんで間違うんや」。テンポが合わないと「オマエが悪い」。そんな殺生な、帝王やあるまいし-と文句も出そうになるんですが、もう12年の付き合い。あれも彼なりの演出?-なんて思えてくる。何と言ってもスリル満点の共演は楽しくて仕方ない。最も信頼できる"先輩"ですね。 (談)